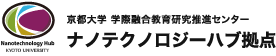初めての方へ
こんなことができないか、こんなことがやりたいがどんな装置が良いか、など
お気軽にお問い合わせいただくことが利用への第一歩になります
はじめに
弊所では、ナノテクノロジー・材料分野をはじめとする様々な研究開発のため、装置および実験室等を供用します。装置および実験室等は、利用者が自ら使用することを前提としています。
また、ご利用にあたっては、所定の利用料金を負担いただきます。
利用料金の詳細につきましては、利用料金等についてをご参照ください。
ご利用いただける方
大学、企業・研究機関などの研究者・技術者のどなたでも広くご利用いただけます。
ご利用形態
技術相談
「利用相談」~「課題登録」後に、各装置に精通した専門の技術スタッフが豊富な経験と専門知識を基に、「加工・デバイスプロセス」や「計測・分析」に関する技術や評価方法についてご相談に応じます。
機器利用
各装置に精通した専門の技術スタッフが、装置の操作トレーニング(オペトレ)を行います。トレーニング受講後は、利用者の習熟度に応じてご自身で装置を操作し、希望する実験を行って頂けます。
薬品,ターゲットなどの実験資材や実験治具の持ち込み、異形サンプルや装置の標準レシピ以外でご利用をご希望される場合は、事前に技術スタッフにご相談ください。共用装置として装置の維持管理や安全管理より、利用の可否を判断させていただきます。
技術補助
操作トレーニング受講後、利用者様が機器を利用してご希望の実験を行われる際に、技術スタッフの支援が必要と判断される場合や利用者が装置の操作に不安がある時など、必要に応じて技術スタッフが適宜、技術的支援を行い、皆様の研究加速をお手伝いします。
技術補助をご希望される場合は、事前に技術スタッフと日程や装置の予約時間の相談を行って下さい。技術補助料金が原則として請求されます。
技術代行
事前に担当の技術スタッフと綿密に打合せを行ってください。またご利用者はできるだけ技術スタッフの行う作業に立ち会ってください。立ち会いが難しい場合でも、進捗について適切にご確認ください。
利用者から指示された詳細な条件及び作業内容に従って、技術スタッフは極力正確な作業実施に努めますが、その結果を保証するものではありません。要求された仕様の試料の作製や評価ができなかったとしても、装置使用料、技術代行料金は原則として請求されます。
共同研究
データ解析や学術的な議論を含めて、利用者と支援機関が成果公開型の共同研究を行い、京都大学の卓越した知の支援が期待できます。研究テーマに応じて関連する研究機関の紹介も行います。
マテリアル先端リサーチインフラ事業(以下、ARIM事業と記載)
利用終了後、A4紙1枚程度の利用報告書を提出していただきます。また、加工・測定等の所定のデータを提供していただきます(データ提供無しの場合には割増料金となります)。
当該報告書は事業ホームページに掲載されます。ただし特許出願や論文投稿等で利用報告書の公開を見合わせたいとのことであれば、最長2年までの公開猶予制度もあります。
詳細につきましては、利用報告書の提出について、データ提供についてをご参照ください。
自主事業(利用非公開)
機密性の高い(利用報告書の提出を控えたい)利用の場合の選択肢となります。
当サービスのご利用料金はARIM事業に比べて割増しとなっております。予めご了承ください。
安全・衛生などについて
弊所において化学物質を取り扱う場合、関連する京都大学の管理規定に従っていただきます。
薬品等(レジスト類を含む)の持ち込みは原則としてお断りします。必要な場合は、弊所で薬品等の手配を代行しますのでご相談ください(実費をお支払いいただきます)。
ただし、使用を希望する薬品、あるいはやむを得ず持ち込む薬品等および材料が規定に抵触しなくても、弊所が装置等の汚染の恐れ等が予想されると判断するときは、その物質の使用を禁止もしくは制限することがあります。
弊所が供用する装置等の利用に際し、労働安全衛生の観点から利用者に対し事前の健康診断、しかるべき資格の保有、しかるべき教育の受講を条件とすることがあります。
弊所の利用中における事故等に備え、利用者は適切な保険に加入しください。
- その他
■ 軍事目的・兵器開発のための研究での弊所のご利用は、固くお断りします。また、弊所施設、装置利用にあたっては、利用者が外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替等令等の安全保障輸出管理に関する法律、政令等を遵守することを前提とします。
■ 施設内ではLAN、TV会議システムが利用できます。PCなどを持ち込まれる場合は、ウイルス対策が適切にとられていることを条件とします。クリーンウエア、ブーツ、無塵紙は弊所で用意しているものを使用いただけます。必要な場合は、職員と相談いただき、ご自身のものを持ち込んでいただくこともできます。
秘密保持について
京都大学ナノテクノロジーハブ拠点では業務を遂行する上で知りえた、利用者側にとって機密である旨を文書で明示された技術上の情報(口頭開示後速やかに書面にて機密である旨を明示された情報も含みます)、すなわち「秘密情報」について、守秘義務を負うものとします。
ただし、秘密情報が次の各項目のいずれかに該当する場合、または適用法令による開示義務、もしくは法令に基づいて主務官庁や裁判所等公的機関から開示請求を受けた場合に、必要かつ相当な範囲で開示する場合は、この限りではありません。
(1)利用者から開示を受けた際、既に自らが所有していた情報。
(2)利用者から開示を受けた際、既に公知又は公用であった情報。
(3)利用者から開示を受けた後、自らの責によらずに公知又は公用となった情報。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に入手した情報。
(5)利用者が事前に文書により開示を承諾した情報。
利用者相互における秘密保持に関しては、利用者自身の管理に委ねるものとし、弊所は一切の責務を負いません。